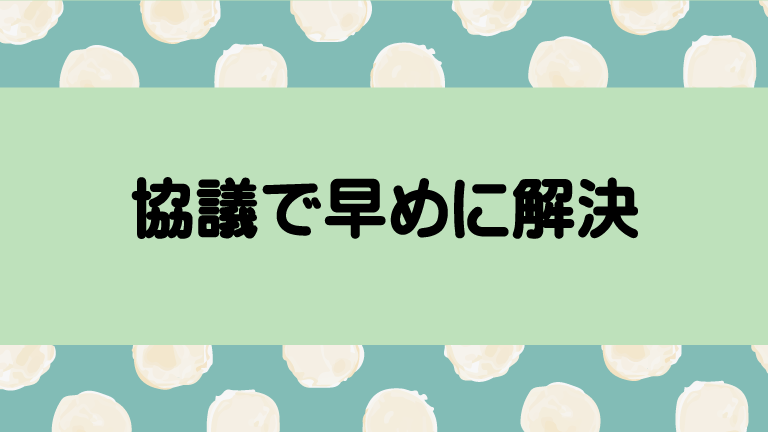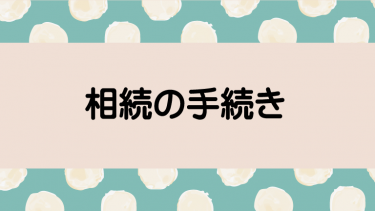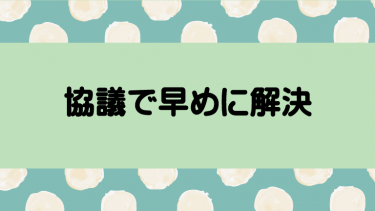1 遺産分割の協議はいつからするべき?
1-1 ルール
亡くなった方の遺産が残っているとき、いつから相続の話をしてよいのか?
お悩みになるかもしれませんが、特に決まりはありません。
最短は、四十九日が終わったころからからでしょうか?相続の話は死のショックから立ち直ってから・・・・ということが多いでしょう。
相続税の申告・納付期限が、相続開始のあったことを知った日の翌日 から10月以内となっているので、これがひとつのきっかけとなり、10カ月でまずは解決を目指すということはあります。
親族で相続の申告期限があるからと、まず協議をしたいといってみるのもよいかもしれませんね。
1-2 アパートなどの収益物件があるとき
しかし、とにかく早く話をしたほうがよいのは、マンション、アパートなどの収益物件が遺産の場合です。借り手がいるのですから、賃料をだれが受け取って借り手とのやりとりをするのか、迅速に決めましょう。
賃料をどうするかで争いがでてきそうなら、誰かの代理人弁護士に管理をしてもらって、収支を報告してもらうというのもよいでしょう。通常、管理会社に委託してそういう報告書をだしてもらうことになります。
このときは、全員がその弁護士に管理を委託するというのは、利益相反から難しいので、誰かが管理をしてその方法として弁護士を使うなど、工夫したほうがよいでしょう。
1-3 相続税との関係
相続税との関係では、実際には、弁護士が関与する多額の遺産があるケースでは、10カ月で解決ができないことが多く、その場合は相続税の納付において工夫が必要です。
遺産分割の協議が終わっていなくても、10カ月という申告期限が迫ってきた場合、相続税申告を行わなくてはなりません。しかし、法定相続分で相続したと仮定して申告・納税を行うことが可能です。つまり、仮申告・仮納税を行うことができるのです。
実際に遺産分割協議ができたとき、調停が成立したとき、税務署に対して修正申告を行い、払い過ぎた人は相続税を戻してもらい、不足している人は相続税を追加で支払います。
未分割のままでは適用できない特例があります。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減特例というような特例ですが、こういうものも、申告期限から3年以内に分割ができれば、適用ができます。
ですから、調停などを利用して、弁護士を介して解決する場合、この3年を目指していることが多いですね。もっとも、これには、当初申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出しておくことが要件になりから、忘れないで出しましょう。
また、申告期限から3年経過してしまったが調停を続けているなどの場合、申告期限後3年が経った日の翌日から2か月以内に、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出することで、判決確定の日などから4か月以内に遺産が分割されれば、これらの特例を適用することが可能となります。
つまり、調停・審判手続きを使って解決しようとしていれば、期間のことはあなり悩まなくて、大丈夫ですね。
こういったルールがありますので、弁護士・税理士とよく相談して特例を使いつつも、納得できる遺産分割を実現しましょう。
申告までに協議を成立させようと一方の相続人が税理士や司法書士に遺産協議案をつくってもらってそれに印を押すように強要する場合がありますが、きちんと時間をかけて結論に達することが可能ですので、そういう強要には負けないできちんと考えて解決させましょう。
仮申告・仮納税をしておけば大丈夫です
2 どういう場合に、遺産分割の協議での解決が可能ですか?
2-1 遺産分割の協議が成立するためには?
遺産分割協議を行うに当たっては、まず3つの重要なことについて、争いがないことが大事です。
これを前提事項などと法律家は呼ぶことがあります。
について争いがないことが必要です。
まとめ : 遺産分割協議ができるためには
* 相続人がだれか?
* 遺産が何で、その価値をどう評価するか?
* 各相続人の具体的相続分はどうなっているのか?
について争いがないことが必要です。
これらについて対立があれば、遺産分割協議はまとまらないでしょう。調停でも話し合いは難しいことが多いです。
2-2 相続人は誰かの争いがあるとき
通常は、相続人は、自分以外に誰と誰が相続人であるかが分かります。
念のため、抜かされた人がいないように、協議の前に、相続人の資格のある者を戸籍謄本等で確認する必要があります。
よって、弁護士にこの点の確認をしてもらったほうがよいでしょう。
たとえば、調べたら「認知された子」がいることもあるのです。
仮に、共同相続人中に、行方不明者などがいる場合、家庭裁判所に不在者の財産管理人という人を選任してもらわないと協議ができません。
2-3 相続財産・遺産は何かの争いがあるとき
分割の対象となるべき相続財産は何と何かがわからないと、遺産分割協議ができません。相続人の間でそれを隠しているひとがいるというような疑義がある場合、なかなか協議は進められないでしょう。
ある財産が遺産かどうかわからないという場合、家庭裁判所の審判の中で判断するか、又は通常の民事訴訟手続で決められます(最高裁判例があります。昭和41年3月2日)。民事訴訟でまずそこを確定してから遺産分割調停を申し立てたほうがよいこともあるので、弁護士と進め方は相談するのがよいでしょう。
遺産分割協議で難しいのが不動産の評価です。
不動産をほしいと考えるひとがそれを低く評価したがります。お金でほしいという人は高く評価したがります。そのために、なかなか合意ができないのです。
遺産分割においては、不動産の評価は市場価格(実勢価格)がつかわれて、公示価格とか路線価、固定資産評価額というような評価はつかわれません。評価でどうしても合意できないときには、不動産鑑定を行って不動産鑑定士に評価をだしてもらいます。
また、いつの実勢価格かというと、その協議をしているとき(相続時ではなく、遺産分割時)となります。
2-3 具体的相続分はどうなっているかに争いがあるとき
各相続人がどういう割合で遺産をもらえるかを、具体的相続分といいます。これは、民法において、定められています。
しかし、遺産分割の協議では、全員が合意さえすれば、法定相続分にこだわらず、自由に相続分を決められます。
また、民法で決まっている特別受益(903条)や寄与分(904条の2)について、遺産分割協議では、これを無視して合意することもできます。
ですから、遺産分割協議とか調停であれば、どんな決め方をしてもよいのですが、通常は自分の相続分をなるべく正確にほしいという相続人は考えるものですよね。
2-4 分割において難しい問題がある財産が遺産の時
遺産によっては、分けるのがそもそも難しいものが含まれていることが往々にしてあります。
- 農地
相続によれば非農家でも所有できますが、農地を細分化してしまう農業が不可能になってしまうかもしれません。よって、農地がある場合で、農業を営んでいる人がいる場合、経営についての一定の配慮は必要です。
- 居住用の土地建物
これについては、現に居住している者の居住利益を考慮する必要がある。 しかし、現実には、都会において居住用の土地や建物が唯一の遺産である場合、代償分割の方法を採るにしても住居取得者の負担する債務額が極め て高額となってしまうことや相続税の高額化の問題もあって、これを売却 せざるを得ず、居住関係の保護が困難な場合が増えている。
- 営業用資産
営業用資産が相続財産である場合、これを分割してしまうと営業継続ができなくなり使用価値がなくなる場合が多いため、できるだけ一体として扱う考慮が必要になる。
- 経営していた会社の株式
被相続人が会社を経営していたり、資産保有法人に不動産を所有させていたような場合、会社の株式の相続については、分割の際に今後の経営をどうするかを考慮して分ける必要がある。
株主が複数で経営上の意見が一致しないと、せっかくもらった会社の株も意味がなくなることがありますし、少数株をもらっても現実には配当がもらえることもなく意味がないということもあります。
- 祭祀供用物
これは系譜(家系図)や祭具(位牌など)、お墓などです。これについては民法898条が決めており、遺産分割・相続の対象になりません。慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するということになります。
3 遺産分割協議はまとめると、どんな効力がありますか?
3-1 遡及効
遺産分割によって各相続人が取得した財産は、相続開始時に、被相続人から直接承継したことになるというのは、民法909条で決められています。
つまり、亡くなった方が亡くなって3年経ってからやっと遺産分割調停が成立しても、そもそも亡くなったときからもらっていたことになります。これを遡及効といいます。「遺産分割には遡及効がある」のです。
もっとも、勝手に遺産分割までに相続人の一人が誰かに不動産を売ってしまっていたような場合、その買った人が何もしらなければその人は保護されます。それが民法909条の但し書きです。
3-2 その他の効果
債務についての分割の効力については注意が必要です。
ローンなどの債務は、通常可分債務となっているので、遺産分割の対象にはならないというのが実務的な考え方です。
法定相続分と異なる方法で債務を分割の合意をしても、銀行など債権者にはそれは有効にならないとされています。
ですので、実務的には、債務はなるべく相続財産によって、弁済するように弁護士はつとめています。相続債務があると分割は問題が複雑になるので、弁済期がきていなくても、相続財産からなるべく弁済してしまうことが望ましいでしょう。
4 遺産分割協議での弁護士の役割は何でしょう?
遣産の分割協議に、弁護士がかかわる場面としてはまず、①相続人の相談を受け、分割協議の進め方等について、助言するということがあります。
そして、協議の場に立ち会い、特定の相続人の代理人として行動することがあります。
協艤が成立した場合、内容を反映した遺産分割協議書をつくり、協議の結果に従い、遺産を取得した人に移転登記をしたり、預金名義を書き換える等、協議結果を実現する作業をするということがあります。
もっとも、基本的には、弁護士は全体のために働くのではなく特定の相続人の依頼を受けてその人の利益になるよう、その意向に沿うように活動します。
まとめ : 遺産分割協議における弁護士の仕事
➡ すべての相続人のための調整をするひとではない
➡ 自分の依頼者となっている相続人のために仕事をしている
➡ その依頼者が法定相続分以上の財産を欲しがれば、それが実現するようにがんばる
ここで、勘違いをしてはいけないのが、貴方以外が依頼した弁護士は、あなたの利益を守るために仕事をしないということです。依頼者の意向や利益を守るのが弁護士の仕事です。
依頼者の相続割合は25%であっても、依頼者がどうしてもこの土地と建物が欲しいといえば、たとえそれをもらったら割合が40%を超えてしまうとしても、それが実現できるような遺産分割協議書の案をつくり、それに署名押印を求めるのが弁護士です。
もっとも、私は調整役としてはたらきますという弁護士もいないわけではありませんが遺産分割では、潜在的に利益相反がありえますのでそういった活動はうまくいかないこと、トラブルになりやすいことが多く、そのような調整をする弁護士は現在ではあまりいないと思われます。そのようにみんなのために中立の立場で調整しているという弁護士がいたら、本当に中立な立場だけで仕事をするのか確認をしたほうがよいかとおもいます。多くの場合、中立だと思い込んでいることが多いからです。
たとえば、「私はAさんから委任を受けている代理人の弁護士ですが、皆さんが納得できるような案を考えました」といって、弁護士から協議案が提案された場合、あくまでもそれは「Aさんの意向」で作られたものです。
そこでは、Aさんの法定相続分を超えていないようになっていることは十分ありえます。もちろん、相続分に従っていて、超えていないこともあるでしょう。しかし、その弁護士はあくまでもAの意向を受けて仕事をしているのです。
5 遺産分割と弁護士の利益相反(複数の相続人を依頼者とする弁護士)
遣産分割協議において、弁護士を依頼する場合、特に注意すべきことは、一人の人の弁護士が複数の相続人の代理人とする場合です。
共同相続人は、遺産分割については、基本的に各自がひとつのものを取り合う関係にあるので、利害が対立する関係にあります。
もっとも、共同相続人がいくつかのグループに分かれていることが多く、そのグループ内では、遺産分割に関する意見がほとんど一致していることはよくあります。
たとえば、5人の相続人のうち3人はみんな不動産は欲しくない、売ってしまってお金で分けたいと思っているというような場合です。
そのように「まとまったグループ」で一人の弁護士を依頼することは、よくあります。ひとりひとりが依頼すると費用が高くなり、また、打ち合わせをするにも大変だからです。
けれども、たとえば上記の事案で、3人のうちひとりが調停がすすむにつれて、誰かの特別利益の主張をはじめ、それが同じグループの相続人であるということもありえます。土地をうりたいといっていた人が、やはり欲しくなってしまったような場合などです。
そうなるとそのひとりの弁護士がそのグループにいた複数の相続人を代理
することはできなくなります。
このような先の状況変化がありえることを理解したうえで弁護士費用の負担を当事者で決めて利益相反が起きたときにはどうするかについて、弁護士とも決めておく必要があります。
また、調停の成立段階では、一人の弁護士が複数の相続人を代理したまま調停を成立させることは、利益相反する双方の代理人になることで許されないとされているので、成立直前に辞任するというのが実務でなされる方法です。
当事務所ではグループの相続人からの受任については、なるべく回避するべきであると考えており、グループの相続人の利益相反状況が発生しない可能性が高いような場合にのみ、利益相反が現実化した場合の弁護士の辞任の可能性についてご理解を頂いてから、受任しています。
遺産分割の場合の利益相反は難しい問題がありますが、東京弁護士会のLIBRAという雑誌の2008年11月号から2009年1月号において、野々山哲郎弁護士が問題を弁護士の視点からお書きですので、詳しく知りたい方は参考にされてください。
https://www.toben.or.jp/message/libra/
利益相反が顕在化したとき、すべての相続人についての辞任までは求められていないのですが、辞任等の適切な措置が弁護士には求められています(弁護士職務基本規程)。